【特別企画】第11回 京都迎賓館文化サロン「有職工芸~王朝のかたち~」の開催とお申込みの開始について
- 特別参観
- 2024年11月06日
第11回 京都迎賓館文化サロン「有職工芸~王朝のかたち~」
日本の伝統技能や文化をテーマとした、京都迎賓館にゆかりのある講師による講演と、少人数での館内ガイドツアーにご参加いただける
「京都迎賓館文化サロン」の開催をご案内します。
第11回は、有職彩色絵師の林美木子氏を講師にお迎えし、有職工芸や王朝文化のしつらいについてご講演いただきます。
当日は講演に加え、NHK大河ドラマ「光る君へ」で使用した檜扇の下絵を含む林氏の貴重な作品の展示及び解説も行っていただきます。
また、通常の一般参観では公開していない、首脳会談等が行われる「水明の間」を含めた館内ガイドツアーを実施いたします。
色彩あふれる工芸作品から王朝時代の美意識を感じていただける大変貴重な機会となっております。是非お申込みください。
令和7年2月13日(木)
- 午前の部
- 9:25集合 10:00開始 12:40終了(予定)
- 午後の部
- 13:25集合 14:00開始 16:40終了(予定)
主な内容

<経歴>
有職彩色絵師。1966年、重要無形文化財『桐塑人形』保持者(人間国宝)である林駒夫の長女として京都に生まれる。
1984年、京都市立銅駝美術工芸高等学校(現:京都市立美術工芸高等学校)日本画科卒業。1986年、京都芸術短期大学(現:京都芸術大学)日本画コース卒業。翌年より丸平大木人形店で人形彩色絵師の仕事を始める。
父・駒夫に師事しながら、有職彩色絵師として、平安の古より連綿と続く伝統的な有職の貝桶、貝覆 、檜扇をはじめ、有職大和絵による板絵などの作品を制作。以降、個展やグループ展を中心に幅広く活動。
2018年「ブルガリ アウローラ アワード 2018」を受賞。
著書に『王朝のかたち』(猪熊兼樹共著・淡交社刊)がある。
NHK大河ドラマ「光る君へ」で使用した檜扇の制作等に携わる。

平安京を中心とする宮廷の建物や工芸品及び礼儀作法には決まった形式があり、その決め事を「有職」と呼ぶ。日本の伝統的な宮廷の姿を実現する知識のことである。
有職という言葉は、「有識
」と記していたものが変化したもので、もとは幅広い知識を有するという意味がある。それが後に宮廷で行われる儀式や行事の厳格な礼法についての知識を指すようになり、また有職と記して「ユウショク」や「ユウソク」と呼ぶようになった。有職工芸もこのような決まり事に則って作られ、日本人の美意識が詰まった工芸品とされる。
京都迎賓館で展示する有職工芸

檜扇「大翳」林美木子氏

有職織装束「顕文紗撫子丸文」
喜多川俵二氏(人間国宝)

熨斗飾り 林駒夫氏(人間国宝)
(熨斗押さえは林美木子氏)
144名(午前の部72名 午後の部72名)
料金
- 一般
- 5,000円
- 大学生・専門学生等
- 3,500円
- 中高生
- 1,500円
※小学生以下の方の申込みができません。
※有効期間内の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳もしくは被爆者健康手帳またはMIRAIROをお持ちの方と介護者(1名まで)は、無料となります。
※中高生または大学生の方は、参観当日に必ず受付で生徒手帳又は学生証をご提示ください。
お申込み
京都迎賓館ホームページにて先着順で事前予約を行います。
事前予約で上限に達しなかった場合や、直前のキャンセル等で当日空きがあった場合は、当日整理券を配布いたします。
【申込みフォーム】
https://form.geihinkan.go.jp/entry/P01?lang=ja&place=kyoto
※国公賓等の接遇、その他運営上の都合により中止となる場合があります。
※当日はメディアによる取材が入る可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※小学生以下の方は申込みができません。

通常非公開の「水明の間」
アクセス・集合場所
- 住所
- 京都市上京区京都御苑23
- 集合場所
- 清和院休憩所
詳しくは、京都迎賓館アクセスページをご覧ください。
注意事項
入館にあたっては、以下についてご協力願います。
①咳や発熱など風邪の症状、息苦しさや強いだるさなどの症状がある方は、参観することが出来ませんのでご了承願います。
②今後の情勢の変化等により、上記の取扱いを変更する場合がございますので、ご注意ください。
最新情報は公開日程ページ及び京都迎賓館公式Xをご確認ください。
お問合せ先
- 京都迎賓館テレフォンサービス
- 075-223-2301(対応時間:一般参観公開日の9:30~17:00)
京都迎賓館文化サロンとは…
日本文化のより一層の理解促進、ひいては伝統文化の継承・発展に寄与することを目的として、当館にゆかりのある「伝統技能や文化」に関するテーマ毎に「文化サロン」を継続的に実施しています。
これまでに開催した京都迎賓館文化サロンの様子

第1回「日本庭園」(平成30年12月)

第2回「京料理」(平成31年3月)

第3回「現代和風建築」(令和元年7月)

第4回「いけばな」(令和元年9月)

第5回「人形と京都」(令和2年2月)

第6回「呈茶」(令和2年9月)

第7回「綴れ織物」(令和4年12月)

第8回「截金」(令和5年8月)

第9回「箏曲」(令和6年2月)

第10回「漆工芸~螺鈿~」(令和6年8月)
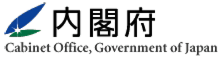
![京都迎賓館 [SP]](https://www.geihinkan.go.jp/wp-content/themes/geihinkan/assets/img/kyoto/common/toplogo_kyoto_sp_bk_ja.png)
![京都迎賓館 [PC]](https://www.geihinkan.go.jp/wp-content/themes/geihinkan/assets/img/kyoto/common/toplogo_kyoto_bk_ja.png)